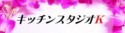本当に暑い日が続いています。
食欲が落ちて冷たいもの、さっぱりしたものばかり食べていませんか?
高い温度の室内では、すぐに食べ物が傷んでしまったり、食中毒も気になります。
今日は以前ほど騒がれなくなった『アニサキス』について
「これからも多くの方に安全で安心して刺身やお寿司を食べて欲しい!」
そのような思いでこちらの記事(以前公開したアメブロ記事より追記編集)を書きます。
『アニサキス』は夏限定の食中毒ではありません。1年を通してご注意頂ければ幸いです。
アニサキスについて
飲食に従事する方は
アニサキスに関する知識は当然のように持っていなければ
いけないのですが、
それ以外の方々はテレビで報道されるようになって
『アニサキス』という言葉を初めて聞いたなんて方もいらっしゃいますよね。
朝の羽鳥さんの番組で特集していたものが
非常に分かりやすかったので
そちらを軽くまとめ、私の知識を追加しご案内します。
アニサキスはどんな魚介にいるのか?
日本人が食べているほとんどの魚介類にいる。
「すじこ」にもいるので、それをほぐした「いくら」にもいる。
鯖に関しては75%も存在 ∑ヾ( ̄0 ̄;ノ
貝にはいないそうです。
アニサキスはどこにいるのか?
海の中なのですが、食物連鎖によって人間の体内にまで
入ってくる可能性がある。
食物連鎖って何?
アニサキスを食べたアミ海老など海の中の小さな微生物が子魚の口に入り
子魚を食べた中型の魚。そしてそれを食べる大型の魚。
そうです!すでにお気づきの方もいらっしゃるように
一番最後は鯨 ∑(-x-;)
なので・・・
アニサキスが一番いる魚は鯨。
鯨のお腹の中は快適な環境。
そこで卵を産み。排泄物と一緒にまた海へ。
これが食物連鎖!( ゚ ▽ ゚ )
どの段階にしろそれらを人間が食べるので
的確に調理が行われていない場合は
アニサキスが体内に入ってくる (((゜д゜;)))
アニサキスで食中毒を起こさないようにする安全な調理とは?
- ◎内臓から筋肉へ移動するため、鮮度の良い魚を使い、内臓を手早く取り除く。
- ◎加熱調理する。(60℃では1分、70℃以上で瞬時に死滅。)
- ◎マイナス20度以下で24時間冷凍する。
〆鯖などは一度冷凍すると安全性が高まる。
- ◎生で食べる場合は目視で取り除く。
アニサキスを発見する機械も開発されたとか。超高そう~((>д<)))
アニサキス自体は白い色の寄生虫ですから、
色のついたまな板で調理すると発見はしやすいです。
- ◎たたきにして魚の身を切り刻む。
烏賊などは包丁で切り込みを細かく入れる。
- ◎よく咀嚼する。
注意:酢や塩、ワサビなどでは死にません!
アニサキスが体内に入るとどのような症状がでるの?
チクチクと胃壁や腸壁を噛みついたりするから痛みを感じる(腹痛)
アレルギー反応を起こします。
アレルギー反応なので、
アニサキスを1回食べたからすぐに激痛が走るわけではなく
数回以降が多いとのこと。個人差ありです。
下記の厚生労働省のサイトにアニサキスのことは詳しくかかれています。
更に知識を深めたい人は御覧くださいませ。
厚生労働省 「アニサキスによる食中毒を予防しましょう。」
回転ずし。スーパーなどの刺身は大丈夫なのか?
と思っている方も多いのではないでしょうか?
・大手さんは上記に書かれた的確な調理を行っている。
・養殖の魚を使用(餌が違う。)
・世の中的に一時騒がれたことで、プロの方々は更に緊張感を持って調理してくれているはず。
勿論、個人店だって頑張っていますから
応援してあげて下さいね!!
アニサキスによる食中毒が10年前に比べて20倍に増えた!
と言われていますが、これは
『2013年からアニサキスによる食中毒が出た場合、届け出が義務付けられたこと。』と
『生で魚を食べる機会が増えた。』ことが考えられています。
あとは・・・
鯨の種類。回遊の関係で、アレルギー反応を起こさせるアニサキスは、太平洋側の魚に多く、日本海側の魚に少ない。
こんな事情もあるそうですよ。
これからも皆様が今まで通り
美味しくお魚が食べられることを願っています!!
本記事のアイキャッチ画像はお刺身3種盛り。
旅館の調理指導のお仕事もしております。
お皿を変えるだけで同じ料理の印象が全く違います。
料理って本当に面白い!